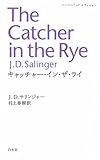
キャッチャー・イン・ザ・ライ (ペーパーバック・エディション)
- 作者: J.D.サリンジャー,J.D. Salinger,村上春樹
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2006/04
- メディア: 新書
- 購入: 11人 クリック: 73回
- この商品を含むブログ (189件) を見る
Amazon.co.jp
1951年に『ライ麦畑でつかまえて』で登場してからというもの、ホールデン・コールフィールドは「反抗的な若者」の代名詞となってきた。ホールデン少年の物語は、彼が16歳のときにプレップ・スクールを放校された直後の生活を描き出したものだが、そのスラングに満ちた語り口は今日でも鋭い切れ味をもっており、ゆえにこの小説が今なお禁書リストに名を連ねることにもつながっている。物語は次の一節で語りだされる。
――もし君が本当に僕の話を聞きたいんだったら、おそらく君が最初に知りたいのは、僕がどこで生まれただとか、しみったれた幼年時代がどんなものだったかとか、僕が生まれる前に両親はどんな仕事をしていたかなんていう「デビッド・カッパーフィルド」調のやつなんだろうけど、僕はそんなこと話す気になんてなれないんだな。第1、そんなの僕自身退屈なだけだし、第2に、もし僕が両親についてひどく私的なことでも話したとしたら、2人ともそれぞれ2回ずつくらい頭に血を上らせることになってしまうからね――。ホールデン少年は、教師をはじめとしてインチキなやつら(いうまでもなくこの両者は互いに相容れないものではない)と遭遇することになるのだが、こうした人物に向けられる風刺がきいた彼の言葉の数々は、10代の若者が誰しも味わう疎外感の本質をしっかりと捉えている。
「歴史的名作」をあらためて読んでみるシリーズ。
この『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、「10代少年少女のバイブル」みたいなイメージがあるのですが、僕が本当に10代だったときは、正直、あんまり好きになれない作品でした。
読む人の多くは、主人公・ホールデン・コールフィールドに感情移入してしまうのだろうけど、高校時代に寮生活をしていた僕は自分が周囲からアックリーやストラドレイターに見えていたんじゃないか、と思えてしょうがなくて。いや、ストラドレイターってことはないだろうな、やっぱりアックリーか……
僕はホールデン・コールフィールドのような「反抗するだけのバイタリティ」がなく、また「教室の窓ガラスなんていくら割っても世界は変わらないよ」と尾崎豊を聞いてバカバカしいと思っていたティーン・エイジャーだったのですよね。
だから、周囲に向かって、「愛読書は『ライ麦畑でつかまえて』です」と言えるような同級生たちを、なんだかとてもうさんくさいというか、「ステレオタイプの反抗的な若者だな」と感じていました。
実は、村上春樹さんの新訳が出てからも、何度か読もうとしてみたのですが、どうも弟のグローブのエピソードくらいで集中力が途切れちゃっていたんだよなあ。
しかしながら、今回は一気に最後まで読むことができました。
「子供に悪影響を与える小説」だと大人は思っているはずの『キャッチャー・イン・ザ・ライ』なのですが、この物語、後半になればなるほど、ホールデン・コールフィールドは「静かに牙を抜かれていく」のです。「反抗心」のかたまりであったはずのホールデンは、自分よりも若い(そして純粋だと思っていた)妹に「大人からみた自分自身の姿」を見せつけられ、困惑させられることになるのです。
最後まで読んで、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』って、「自分の順番」が終わりに近づいたことに懸命に抵抗している若者の足掻きの小説なのではないかな、と30代後半の僕は感じました。
そして、どんなに足掻いても、いつか「終わり」は訪れる。
でもね、この博物館のいちばんいいところは、なんといってもみんながそこにじっと留まっているということだ。誰も動こうとはしない。君はそこに何十万回も行く。でもエスキモーはいつだって二匹の魚を釣り上げたところだし、鳥たちはいつだって南に向かっているし、鹿たちはいつだって溜まりの水を飲んでいる。素敵な角、ほっそりしたかわいい脚も同じ。おっぱいを出したインディアン女はいつだって同じ毛布を織っている。みんなこれっぽっちも違わないんだ。ただひとつ違っているのは君だ。いや、君がそのぶん歳をとってしまったとか、そういうことじゃないよ。それとはちょっと違うんだ。ただ君は違っている、それだけのこと。今回君はオーバーコートを着こんでいるかもしれない。あるいはこの前に列を組んだときの君のパートナーは、今回は猩紅熱にかかっていて、君には新しいパートナーがいるかもしれない。あるいは君のクラスを今回率いているのはミス・エイグルティンガーじゃなく、代理の先生かもしれない。あるいは君はバスルームで母親と父親が激しい喧嘩をしているのを耳にしたあとかもしれない。あるいは君はさっき通りがかりに、水たまりにガソリンの虹が浮かんでいるのを目にしたかもしれない。つまり僕が言いたいのはさ、君はなんらかの意味でこの前の君とは違っているということなんだ。うん、うまく説明できないんだけどさ。それにもしうまく説明できたとしても、いちいち説明したいっていう気になるかどうかはわからないね。
僕はこれを読みながら、これほど「うまく説明できている」文章というのは、そんなにないんじゃないかと感じました。この文章は、たぶん16歳の僕には、頭では理解しているつもりでも「実感」できてなかったのですけど、いま読むと、「変わらざるをえない存在」として生きてきたことのせつなさに押しつぶされそうになってしまいます。
ホールデン・コールフィールド少年は妹のフィービーに「好きなこと」を問われて、自分がやりたいたったひとつの仕事についてこんなふうに語っています。
だだっぴろいライ麦畑みたいなところで、小さな子どもたちがいっぱい集まって何かのゲームをしているところを、僕はいつも思い浮かべちまうんだ。何千人もの子どもたちがいるんだけど、ほかには誰もいない。つまりちゃんとした大人みたいなのは一人もいないんだよ。僕のほかにはね。それで僕はそのへんのクレイジーな崖っぷちに立っているわけさ。で、僕がそこで何をするかっていうとさ、誰かその崖から落ちそうになる子どもがいると、かたっぱしからつかまえるんだよ。つまりさ、よく前を見ないで崖の方へ走っていく子どもなんかがいたら、どっからともなく現れて、その子をさっとキャッチするんだ。そういうのを朝から晩までずっとやっている。ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ。
なんだか、今回あらためて読んでみたら、この場面で涙が出そうになって。
僕も「そういうもの」になりたかったはずなのに。
「10代のときに読んでおくべき本」だという先入観を持たれがちなのですが、大人には大人の読みかたができる作品です。
この『キャッチャー・イン・ザ・ライ』そのものが、僕たちの「変化」を横目に留まっている博物館みたいなもの、なのかもしれません。




