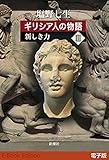- 作者:青木 健
- 発売日: 2020/08/19
- メディア: 新書
Kindle版もあります。
ペルシア悲劇、ペルシア絨毯を生んだ、哀調を帯びた神秘的な桃源郷。しかし、古代オリエント期のペルシアは、リアリズムの極致というべき世界だった!急激な都市化、海のシルクロードの掌握がもたらす経済的繁栄。西アジアからエジプトまで支配するに及んだ壮大な組織力と軍事力。くりかえされる宮廷クーデターと兄弟間の殺戮…。そしてリアリズムの塗料が剥げ落ちた時、古代ペルシアに衰亡が忍び寄る―。
「ペルシア帝国」といえば、映画『300』で、ケバケバしく身を飾った王が、象と大軍を引き連れて、スパルタの勇士たちを圧殺しようとしているのが、僕のイメージなんですよ。
正直、「ペルシア帝国」絡みの歴史的な出来事で思い出すのは、ギリシアに大軍で攻め込んで結局撃退された「ペルシア戦争」と、大軍を擁しながら、日の出の勢いのマケドニアのアレキサンダー大王に負けて、一気に滅亡してしまったこと、くらいなのです。
日本の世界史教育というのも「ヨーロッパ史重視」なんだよなあ、とあらためて考え込んでしまいます。あとは「王の目」「王の耳」というのもあったなあ。これは、言葉として面白かったから記憶に残っていたのですが。
先日、中公新書で『ビザンツ帝国』という本を読みました。帝位を争った人たちが、敗れると「摘眼刑」にされまくっていて、刑罰というのも国によって違うのだな、と感心したのです。いちばん印象に残っているのがその話というのも、なんだかなあ(ちなみに、ペルシア帝国でも「摘眼刑」の記述が散見されます。ビザンツ帝国ほど頻繁ではありませんけど)。
古代ペルシア研究を推し進めるうちに筆者が愕(おどろ)いたのは、その壮大な組織力と現実主義であった。イスラーム化以後のペルシアの、あの現実剥離の形而上学的特質の対極にあるかのような「古代ペルシア」の現実に対する構築性は、如何にして生み出されたのだろうか? 人類文明発祥の地たるメソポタミアは、ついにオリエント全体を統一するような強大な王権を生み出さなかったが、僻陬(へきすう)の地たるペルシアの方で、かえって優れた組織力を見せ、魔法の杖の一振りでオリエント全体を軽々と取り纏めてしまったのである。
これがただ一度限りのことであれば、神の気紛れとして片付けることもできよう。しかし、何たる不条理か、500年以上の間隔を空けて二度までも、この高原砂漠ペルシアの地から興起した王朝が、オリエント全域を覆ったのである。この古代ペルシアの意表外の万能性には、イラン学者として瞠目せざるを得ない。筆者は、この現実的組織力の点──及び思想的貧困の点──で、メソポタミアに対する(古代)ペルシアは、ギリシアに対するローマに相当すると捉えている。
古代ペルシアは、如何にもペルシアらしく、思想文化の面でも、独自性の発揮によってではなく、その集大成化によって貢献したのである。
それらのことどもよりも、古代ペルシアの驚倒すべき点は、あれだけ多民族──定住民も牧畜民も遊牧民も含めて──が跋扈するオリエントの地を、最初は220年間にわたって、つぎには427年間にわたって、かなりの程度の調和と持続力を以って統治した点にある。これが、夢と観念の世界に遊ぶイスラーム期のペルシア人とは似ても似つかぬ、リアリズムの極致を窮めた古代ペルシア人の姿である。もっとも、そのリアリズムとは、要するに叛乱を起こした者が居たら、容赦なく頭をぶっ叩くまでの話であって、軍事力を背景とした政治的エネルギーと言い換えても可である。
本書では、古代ペルシアのエネルギーが拠って来るところを、ハカーマニシュ朝における大王の宮廷政治と、サーサーン朝における皇帝と大諸侯との鬩ぎ合いに見る。
この新書では、ハカーマニシュ朝とサーサーン朝の歴史が語られていくのですが、馴染みがない、似たような名前の王の連続や、聞き慣れない地名など、読むのにはけっこう時間がかかりました。上記の引用部にもあるように、著者の文章の格調高さも、好みが分かれると思います。
ただ、もし外国人として日本の歴史を学ぶとしたら、やっぱり、「なんでこんなに似たような名前ばっかりなんだ……」「地名がピンと来ない……」という感じになるでしょうから、致し方ないところではありますよね。
前述した『ビザンツ帝国』もそうなのですが「世界史で習ったことはあるけれど、『名前を知っているだけ』」という国の歴史をこうして一冊の新書で知ることができるようになったのはありがたい。
この本を最初から最後まで読んで、ハカーマニシュ(アケメネス)朝とサーサーン朝の歴史を概観したあと、僕は「あれ?」と思ったんですよ。ペルシア戦争でギリシャのポリスと戦ったのは、「ペルシャ帝国」だったよなあ、って。
読み返してみると、「カリアスの和約」について触れているくだりが少しあるくらいで、「ペルシア戦争」は、ほぼスルーされているんですよ。
個人的には「ペルシア側からみた、『ペルシア戦争』」に興味があったので残念ではありますが、これは、ペルシア帝国からみたら、「ペルシア戦争」は、さほど歴史的に大きな出来事ではなかった、ということなのかもしれません。「ギリシャ・ローマ側からみた歴史」では、大きなイベントであったのだとしても。
この本を読むと、帝国内ではしょっちゅう兄弟での後継者争いとか、帝国内の叛乱の鎮圧などで軍事行動が行われていて、ペルシア戦争もペルシア側からすれば、「辺境でのちょっとした挫折」くらいのものだったのかもしれません。当時のペルシアの人々がどう思っていたかというのは、今の僕には想像しようもないのですけど。
アレキサンダー大王に敗れ、帝国が急激に崩壊していった経緯に関しては、「ペルシア帝国側の要因」について言及されています。
このように、必ずしも各地のクシャサパーヴァン(総督)に権威を承認されたとは言い難い新大王(ダーラヤワウシュ三世)が即位し、西部諸州の独立傾向が止まらないなか、紀元前334年の春にマケドニア王国のアレクサンダー三世──言うまでもなく、フィリッポス二世の息子である──が三万人規模の軍を率いて、「帝国」への侵攻を開始した。西洋史の観点から見れば、続くアレクサンダー三世の軍事的成功は彼の天才を示すものとされるが、イラン史の観点から見れば、解体傾向に歯止めのかからない「帝国」に、絶好のタイミングで侵入したとも言える。
アレキサンダー大王は確かに「天才」だったけれど、ペルシア帝国の側にも、「敗因」はあった、ということなのです。
アレキサンダー大王であっても、ペルシア帝国の隆盛期であれば、攻め滅ぼすことは難しかったかもしれません。
そういう「タイミング」みたいなものに恵まれるのもまた、「英雄」の条件ではあるのでしょうね。
帝国の経済力を顧みず、世界大戦を引き起こしてサーサーン朝を一気に凋落させたホスロー二世や、王の寵姫を酷い目にあわせた正妻のエピソードなど、歴史というのは、それぞれの地域に個性がある一方で、洋の東西を問わない「権力者がやってしまうこと」というのがあるみたいです。
ギリシア・ローマ史、ビザンツ帝国史とあわせて読むと、さらに面白くなる本だと思います。

- 作者:中谷 功治
- 発売日: 2020/06/22
- メディア: 新書