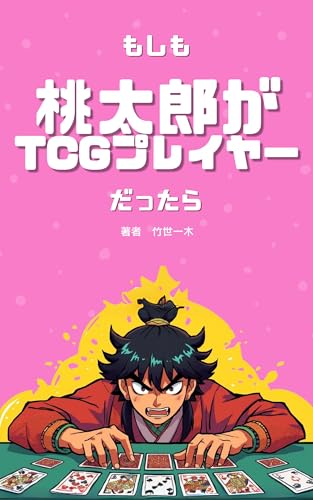Kindle版もあります。
プロカードゲーマー直伝
勝利をつかみ取る史上初のTCG理論書!!!
MTG ポケカ 遊戯王 デュエマ ワンピカ etc.
あらゆるプレイヤー必須の本質的思考法ゲームとして、競技として――多くの人が魅了され、勝利を目指して打ち込むトレーディングカードゲーム。
ゲームの本質、確率的センス、認知バイアス、メタ読み、練習方法、言語化、デッキ構築の視点……
どのTCGにも共通するセオリーがここにある。カードゲームの本質は「数理と心理」である――勝てると思ったのに勝てないのはなぜか。カードゲームはどのようなもので、その実力とは何か? プロプレイヤーとしての経験から得られたどのカードゲームでも充実して強くなれる理論をお伝えします。
今は、僕自身がカードゲームを手にとることはほとんどないのですが、僕の子どもたちは、トレーディングカードゲームがけっこう好きで、ときどきやっているようです。
僕も、子どもの頃、ボードゲームは大好きだったし、ゲーム機で『カルドセプト』とかをやっていた記憶はあるのです。
この本、プロカードゲーマーである著者が「トレーディングカードゲーム(TCG)」で「本当に」強くなる「考え方」について書いた新書です。
わざわざ、「本当に」と「」で括ったのは、僕もこの本を読むまでは、こういうカードを組み合わせてデッキをつくり、こんな作戦で戦えば勝てますよ、大会でいい成績をおさめられますよ、という具体的な内容が書かれていると思い込んでいたからです。
実際に読んでみると、書かれているのは、統計学と確率論、行動心理学の話が主で、いまこうやると勝てる、というよりも「どういうスタンスで研究・検討していけば、TCGでの勝率が上がるのか?」でした。
正直なところ、ほとんどのプレイヤーは、これを読んでもすぐに強くはなれないし、そもそも、書かれていることを自分なりに消化して、ゲームに活かすのも難しいのではないかと思います。
だから役に立たない、というのではなくて、本当に長い目でみて人生で役に立つのは、「いまのこの状況での攻略法」ではなく、「どうやって、状況の変化に対応して、新しい攻略法を自分なりに編み出していくか」なんですよね。
世の中には、かつて自分がうまくいったやりかた、それが古くなって時代に合わなくなってもこだわりつづけてしまう人が多いから。
僕はこれを読んでいて、作家の森博嗣先生が以前上梓した本を思い出しました。
森先生は、この本のなかで、「本書の記述はかなり抽象的だから、それぞれの状況にあわせて、自分で解決策を模索してもらいたい」と書いておられます。
具体的にあれをやれ、これをやれ、と書かれていないと、「じゃあ、どうすれば良いんだよ?」と思われがちなのですが、わかりやすいことは、応用がきかなかったり、「考え方を変えましょう」みたいな、それができれば苦労しないよ、って話ばっかりだったりするものです。
TCGというのは、定期的に新しい効果のカードが出てきてゲームバランスが変わっていきます。
この本の著者は「いま勝ちやすい方法」を紹介するよりも、レギュレーションが変更されてもそれに対応して、ずっと強いプレイヤーでいられるような思考法を紹介しているのです。
昔のクラシックなカードゲームやボードゲームと違って、いまのネットを使ったソーシャルゲームや新しいカードが定期的に出てくるTCGの「いま勝ちやすい方法」は、相手に対策されたり、運営側がゲームバランスを調整したりすれば、すぐに通用しなくなってしまうから。
カードゲームは一見シンプルに見えます。ルールは論理的な文章で示され、勝敗条件も明快です。「この相手なら勝てる」と確信に近い期待を持ったこともあるかもしれません。しかし、何十回と対戦を繰り返しながらも、なぜか勝てない状況に悩んだことはないでしょうか。カードゲームには「論理的に考えれば勝てそうなのに、そううまくいかない」という不思議な魅力があります。本書はまず「どうして勝てそうなのに勝てないのか」という問いを正面から掲げるところから始めます。
「勝てそうなのになかなか勝てない」「必勝法」が(少なくとも現時点では)存在しない、どんどんカードやルールが「更新」されていく、というのは、カードゲームの難しさであり、魅力でもあるんですよね。上手いほうが勝率は高いけれど、必ずしも勝てるとは限らない。だからこそ、初心者も「期待」を持てる。
プロカードゲーマーと名乗ると、「カードゲームの強さとはなにか」と聞かれることがよくあります。私は「数理と心理」と答えています。
数理はより正確な判断のために必要です。感覚は誤ります。確率や論理を用いて、単に感覚に判断を任せるよりも正確性を増すことができます。それに対して心理は、相手の行動を読むために重要──と思われがちですが、それは比較的重要ではないと考えています。私が心理の重要性を強調したい理由は、カードゲームをプレイする私たち自身を、私たちはよく知らないということです。
人間は自らの合理性を前提にしています。自分が取るべき行動を合理的に判断できると思い込んでいます。しかし、カードゲームにおいては、自分の行動を合理的に判断できると思い込んでいる人間が、自分の行動を合理的に判断できないことがよくあります。
この節で覚えてほしいことは「当然のことを普通にやることは難しい」ということです。
「合理的な判断」ができるはずの人でも、どんな状況でもためらいなくそれができるわけではないのが現実です。
将棋のプロ棋士でも、そんなに難しくない勝ち筋を見逃して悪手を指したり、株式投資で持ち株が20%下がったら売る、と決めているはずなのに、下落局面になると「この株はまた上がるはず」と未練が出て、さらに傷口を広げてしまったり。
人間関係でも、他人からアドバイスを求められたら「もう関わらないほうがいいんじゃない」と言う状況でも、自分のこととなると、なかなか「切り捨てる」のは難しい。
株主優待で生活していることで有名になった桐谷広人さんが株で成功できたのは、将棋を通じて、「自分が窮地でどういう行動をとりやすい人間か」を知ることができたのが大きいのではないか、と僕は思っています。
「論理的に考えて結論を出す」ことは難しいけれど、それ以上に「適切なタイミングで、感情に流されずにそれを実行する」のは大変なのです。
だからこそ、プロスポーツやギャンブル、ゲームは面白い、とも言えます。他人事としては、ね。
話を簡単にするために、ダイスロールのギャンブルをしていると考えましょう。連続で1以外を出せば勝ち、1を出せば負けで、最後の一振り! 勝てば掛け金が倍に、負ければゼロになるところで1が出てしまった。6分の1を引いてしまうなんて運が悪い!……同じような状況です。
しかし、このギャンブルが「10回連続で1以外を出せば勝ち」というものだったらどうでしょうか? 最後の最後で1が出たことは確かに不運ではありますが、ギャンブルに勝つ確率は16%程度であるため、そもそもやるべきではないというのが正解です。
これと同じように、終盤での低確率の不運を引いたものの、実はそこに至るまでの過程がめちゃくちゃラッキーだった、ということがあります。これに誤った確率の考え方を用いてしまうと真逆の結論の根拠になることがあります。最後の引きは確かに悪かったとしても、他のデッキならもっと早くにゲームに勝てていたかもしれません。あるいは、そこに至るまでに相手も何度も不運に見舞われていて勝ちを逃していたかもしれません。たとえ部分的に不運でも、それが全体的には幸運であった可能性を考えなければなりません。
本当に上げたいのは勝率です。「あとちょっとで勝てた」として、「あとちょっと」その場面に必要なカードを増やしたら、別のカードを抜いたせいで「あとちょっとで勝てる状況」すら来なくなるかもしれません。確率を考えるとき、その確率はどのような条件の下であるかを勘定に入れなければなりません。
対戦中にプレイヤーがよく言う「〇%であのカードを引ける」「たぶん大丈夫」という考えは、実は何かしらの条件が加わった”特定の条件下での”確率になっていることが多いです。実際、その場面ではそれが正解でったかもしれません。しかし、デッキ選択やそれより以前のプレイを含めた大局的な判断として、それが正解だったという根拠には必ずしもなりません。
確率を単純に割り算で導くのは可能ですが、実際にプレイ中に使っているのは「こういう条件のもとなら〇%」という、条件付きの確率であることがほとんどです。
勝負どころで目先の確率を計算して、「合理的な判断をしている」と考える人は多いのですが、本当に強くなるためには、「自分にもっと有利な確率になる条件にもっていくための大局的な判断や工夫」が求められるのです。
電車の乗り換えを極限までスムースにすることで、目的の場所に間に合ったことに満足する人は多いけれど、飛行機などのほかの交通手段を使えば、もっと余裕をもって到着できたかもしれません。
そんなことは言っていなかったはずなのに、結果が出てから「このデッキが一番使われるのはわかってたよね」。「このデッキが自分も一番強いと思ってたよ」とはじめからそう思っていたかのように言う。手のひらを返して言うことがころころ変わる人にはいい気持ちがしないものですが、大なり小なり誰にも備わっている性質です。
これは心理学では「後知恵バイアス」と呼ばれています。結果を知った際に「最初からそうなることはわかっていた」と思い込んでしまう傾向です。
失敗の重要性に気付けない原因には「流暢性バイアス」も関係しています。ものごとには様々な側面があり、例えばあるカードが強い状況だけを選んで「そのカードが強い理由」を説明することができると同時に、同じように「弱い理由」も説明できるものです。本当の「強い理由」は「強い側面」と「弱い側面」の比較によって説明されるべきですが、「〇〇だから強い!」という単純な説明には妙に説得力を感じてしまうのが人間です。情報が流暢で頭に入ってきやすいほど、その情報を真実だと感じやすくなります。
結果が出た後に、それがあたかも当然のように説明されると、まるで簡単なことのように思えてきます。まるで自分もはじめからそう思っていたかのように錯覚してしまうことすらあります。実際には、結果がわかってから「あのときこうすればよかった」と言っても仕方ありません。思っているほど簡単なことでないからこそ間違えたのではないでしょうか。当時の状況では、限られた情報と時間の中で最善と思われる判断をしたはずです。だからこそ、本当に振り返るべきなのは「ああすれば良かった」ではなく、「どうしてそうできなかったのか?」なのです。
本当に振り返るべきなのは「ああすれば良かった」ではなく、「どうしてそうできなかったのか?」
これは、TCGに限った話というよりは、人生全般にあてはまることだと思います。
さんざん後悔しているはずなのに、僕自身も、人類全体も、同じ間違いを繰り返してしまう。
言うは易し、行うは難し。
「どうしてそうできなかったのか」を少しずつでも考えて、前に進んでいくしかないのでしょう。
すぐにカードゲームでどんどん勝てるようにはならないかもしれないけれど、カードゲーム攻略本を読むつもりで買った子どもや若者たちが、著者のメッセージをより広い範囲で活かせることを願わずにはいられません。
僕も、人生をうまく「攻略」できなかったプレイヤーのひとりなので。