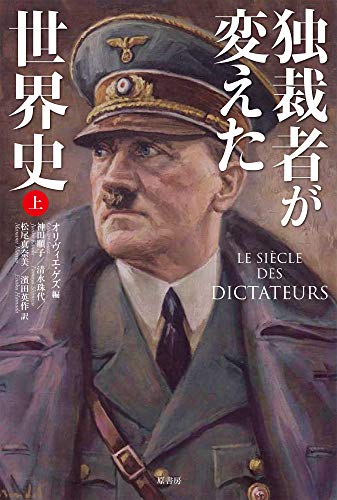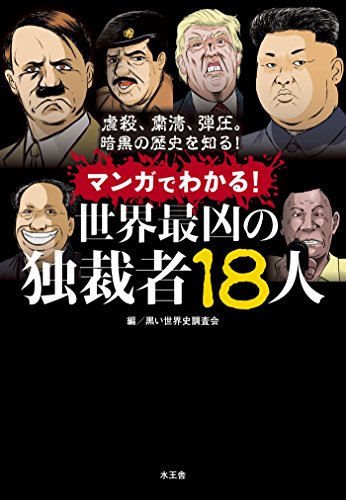Kindle版もあります。
内容(「BOOK」データベースより)
なぜプラトンは「独裁」を理想の政治形態と考えたのか?独裁者の台頭を防いだ古代ローマの知恵とは?革命家ロベスピエールはなぜ独裁者と化したのか?古代ローマ史の泰斗が2500年規模の世界史を大胆に整理し、「独裁」を切り口に語りなおす一冊。繰り返し現れ来る独裁者と、それに抗う人びとによる相克の歴史を読み解く。
「独裁」は悪なのか?
誰かひとりが好き勝手にできるような社会なんて、ダメに決まっているだろ、と僕は長年思っていたのです。
高校生の時に読んだ『銀河英雄伝説』で、民主主義勢力側の主人公であるヤン・ウェンリーという人が「専制政治は、失政を他人のせいにできる、という点で、民主政治に劣っている」というようなことを言っていたのがずっと記憶に残っていますし。
ウィンストン・チャーチルの「民主主義は最悪の政治形態らしい。ただし、これまでに試されたすべての形態を別にすればの話であるが」という言葉も有名ですよね。
しかしながら、新型コロナ禍のなかで、「ほんとうに民主主義はつねに正しいのだろうか?」という疑問もわいてきたのです。
中国では「封じ込め」のために迅速に都市のロックダウンが行われ、個人情報の取り扱いについて議会で論じられることもなく、感染についての情報がスマートフォンで拡散されるようになりました。日本では、手続き上、さまざまな感染対策を強制的にはできず、「自粛警察」が跋扈することになったのですが、「自粛警察」に嫌悪感を抱きつつも、そういう空気がなかったら、もっと感染は拡大しているのではないか、とも思うのです。
この本では、古代ギリシア・ローマの時代からの政治形態の変化が紹介されています。
「独裁政治はなぜ生まれ、滅びるのか。そして、一度滅びても、何度も蘇ってくるのか」そもそも、ヒトラーやムッソリーニのように、民主的な選択(選挙)によって、独裁者が生まれることも少なくありません。
ヒトラーは最悪の独裁者であるのだとしても、彼に投票した人たちに「責任」はないのか?
本書では、世界史を「独裁政」「共和政」「民主政」の視点から読み解き、現代のわれわれが学び、教訓とすべき点を抽出していきたいと思います。
近代にいたるまでの世界史を振り返ってみれば、多くの場合、独裁の歴史だったといっても過言ではありません。立憲君主政の確立──つまり、王権が法律で制限されるようになったのは、17世紀イギリスのピューリタン革命や名誉革命、18世紀末のフランス革命以降のことです。それ以前は、フランス王ルイ14世が「朕は国家なり」と言い放ったように、独裁色の強い絶対君主政が中心だったのです。
独裁政とは、単独の為政者が政治権力を独占する政体を指します。最高指導者が皇帝であれば「帝政」、王であれば「王政」、王位が世襲されていれば「君主政」です。武力で独裁的権力を奪取し、勝手に君主を名乗った場合は「僭主(せんしゅ)政」と呼ばれるのが普通です。
もちろん、独裁を排した国家がなかったわけではありません。「独裁政」への強烈な反発から、古代ギリシアではアテネやスパルタといった都市国家(ポリス)への「民主政」が生まれ、ローマでは「共和政」が500年維持されました。中世ヴェネツィアの共和政はさらに長く、ナポレオンに征服されるまでおよそ1000年続いています。
「民主政」については、くどくどと説明する必要はないでしょう。文字どおり、選挙などによって人民の意志を集約し、それに基づいて行われる政治です。
では、「共和政」とはどのような政体でしょうか。
これは典型的には、古代ローマが採った姿ですが、日本人にとっては非常にイメージしにくいものかもしれません。
しかし欧米人と話していると、独善的な「独裁政」に対比されるのは概して「共和政」で、民主政はその先に出てくる考え方です。一方、日本人の多くは、「独裁政」と「民主政」を対比させて考えがちです。異なる歴史を歩んでいるから仕方のないことかもしれませんが、共和政の知恵に学ばないのは非常にもったいないことだと私は思います。
共和政は、集団による統治を志向する政体で、その点では貴族政や寡頭政に近い部分があります。詳しくは第二部で取り上げますが、ローマ市民で構成する「民会」が、最高指導者「コンスル」をはじめとする政務官を選び、権威と見識を持った貴族で構成される「元老院」が、民会やコンスルに助言するかたちで国政を舵取りしました。
ローマ共和政の肝は、まさに「元老院」にありました。いま述べたように、「権威と見識を持った貴族で構成される『元老院』が国政を舵取りしていた」からこそ、衆愚政治の危険も独裁政の危険も克服しつつ、500年ものあいだ「共和政体」を持続させ、ローマの繁栄を実現させたのです。つまりローマの共和政は、独裁政、貴族政、民主政という三つの政体をバランスよく組み込み、「元老院」を中心として相互チェックをうまく機能させる政体だったのです。
加えて、ローマ共和政のポイントとして挙げられるのは、独裁政に陥らないために独裁的な要素を完全に排除するのではなく、限定的かつ機動的に取り入れて国家運営をしていたことです。つまり、平時は合議を重んじつつ物事を決めていくのですが、大きな戦争が起きた際などは、コンスルに独裁的な権限を与えていたのです。仮に感染症が起きたとしても機動的な対応が可能な体制でした。
この本を読んでいくと、「民主政」=善、「独裁」=悪、と一概には言い切れないことがわかります。人々の熱狂に従ってしまったがために致命的な選択をした国や、危急存亡のとき、有能な人物に任せて苦難を乗り切った事例は、たくさん存在しているのです。
著者は、「民主政」「共和政」「独裁政」の「いいとこ取り」のような形が良いのではないか、と考えているようです。
状況によっては、「独裁的な権力」を誰かに預けて、迅速な判断をしてもらうことも必要だけれど、その期間を限定すること、独裁者に対するチェック機構をしっかりつくっておくことが大事、ということなんですね。
しかし、独裁者というのは「任期を無制限にして、自分に対するチェック機構を骨抜きにしてしまう」ものではあります。
その「独裁的な権力を与えられた人自身の性格や考え方」もそれぞれです。理想に燃えていた指導者が、権力を握って時間が経つにつれ、変わっていくことも少なくありませんし。
ヒトラーが経済政策の成功によって支持を集め、それを足掛かりに独裁体制を固めていったことは、現代の「独裁政」を考える上で重要なポイントの一つだと思います。
世界恐慌が起きたのは、ちょうどロシアにスターリン政権が誕生した1929年のことです。スターリンは、資本主義に未来はないと一刀両断し、自身が展開する五ヵ年計画の成果を事実以上に喧伝して、独裁体制の足場として利用したことが分かっています。経済政策(の喧伝)は、いつの時代も独裁への足掛かりになるのです。
ヒトラーのドイツも、投影経済によって活力を取り戻したように見えました。戦前の日本でも資本主義の限界が声高に叫ばれて、ソ連やドイツに倣って統制経済を進めるべきだとする意見が極めて強くなりました。そして日中戦争が勃発したこともあって、実際に統制経済へと大きく舵を切っています。
資本主義への自由経済が行き詰まりを見せると、「強権を発動して経済活動を統制すべきだ」とか「計画経済を実施すべきだ」と説く人が必ず出てきます。自由主義一辺倒では、収拾がつかない事態も起こりますから、ときには統制を強めることも必要になってきます。大きな政府か、小さな政府か。市場への介入か、放任か。それは現代のわれわれもなお、直面している問題でもあります。
ときに果断な決断が必要なことは間違いありません。しかし、ここで私たちが世界史の教訓として思い起こすべきは、その政策が「悪しき独裁」への糸口に、容易になってしまうことでしょう。
政体について、いろんな考え方はあるのでしょうけど、結局のところ、みんな自分たちの生活や経済のことが大事、なんですよね。
中国は共産党独裁で、国民の自由が制限され、監視社会化していています。
でも、経済成長を続け、生活が豊かになっているので、みんなそれなりに受け入れてしまっているように見えるのです。
アメリカの大統領選挙でも、トランプ大統領が落選したら株価が下がるのではないか、と危惧していた人がいましたし、日本でも安倍首相の辞任発表の直後、日経平均は大きく下げています。
ただ、結果的には、バイデン大統領に決まっても、安倍さんから菅さんに総理大臣が変わっても、株価は上がり続けているのが現状です。
とりあえず、経済成長が続き、人々の生活が(物質的に)良くなっていれば、その時代の為政者は高く評価されるのです。
どんなに問題発言を繰り返したり、公文書を改竄したりしていても。
デジタル化やAI化の進展で人間に十分な時間ができることによって、新たなコミュニティを作れる可能性がある。この姿は、共産主義が理想にしていたこととも重なります。共産主義では、生産力を上げることによって午前中を労働に当て、午後は自分の趣味に当てるような姿を理想として語っていました。
20世紀の歴史のなかで社会主義や共産主義の試みは失敗しました。ただ、それは「平等」を基調とした社会主義や共産主義が失敗したのであって、見方を変えれば、「自由」を基調にした社会主義や共産主義もありうるのかもしれません。そして、それをデジタル独裁という方向が後押しするのかもしれません。
考えてみれば、古代ギリシアやローマの「市民社会」は、労働階級としての奴隷を前提として成り立った社会でした。奴隷に労働を任せておいて、富裕な人たちは趣味や楽しみに没頭することができたのです。そのような姿が、デジタル化、AI化、ロボット化などをうまく使うことで手に入るかもしれないのです。
そのようなことが本当に可能なのか。あるいは、そのような姿が実現したときの問題点はどこにあるのか。そのようなことを考えるにあたっては、古代ギリシアや古代ローマのことを研究するのが、意外な近道になることでしょう。
少なくとも、人類が「歴史」という概念を持つようになったこの数千年単位では、「独裁政」「共和政」「民主政」を繰り返しているわけで、ギリシアやローマの経験に学ぶべきことは多いのではないかと思うのです。