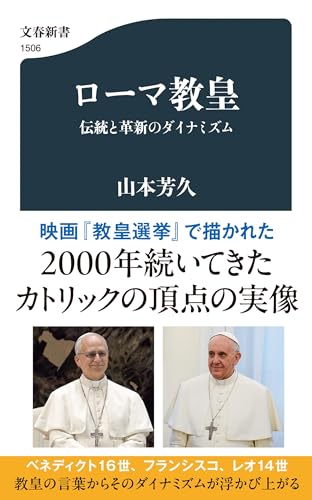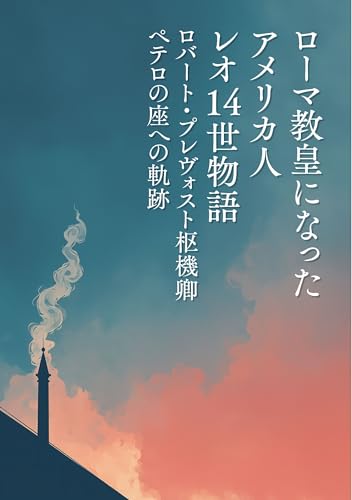Kindle版もあります。
ローマ教皇フランシスコが帰天し、アメリカ人初となる(267代)ローマ教皇が新たに選出された。フランシスコと同じく南米での活動が長く、前教皇の貧しい人々に寄り添う路線を引き継ぐと目されるレオ14世とはいかなる人物か?
映画『教皇選挙』のヒットに続き、フランシスコ葬儀の場でのトランプとゼレンスキーの会談、ヴァンス米副大統領を批判するレオ14世のXでの発言など、国際政治とのクロスにおいてもローマ教皇が再び注目を集めている。
学者から転身したベネディクト16世、世界の分断に橋をかけようと奮闘したフランシスコ、そして19世紀末のレオ13世の名を引き継ぐレオ14世――『聖書』に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。混迷をきわめる国際政治に一石は投じられるのか。
トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論。
僕の記憶に残っている最初のローマ教皇(当時(1970年代)は『ローマ法王』と呼ばれることが多かった)は、ヨハネ・パウロ2世でした。1978年から2005年までその座にあったヨハネ・パウロ2世は、広島・長崎も訪問されています。
あの頃は、『ローマ法王』は、ずっとこの人なのだ、という気がしていたのです。
もちろん、そんなことはなかったのだけれど。
フランシスコ教皇が帰天され、教皇選挙(コンクラーベ)が行われたこと、奇しくもそのタイミングで公開されることとなった映画『教皇選挙』が日本でもかなり話題になりました。
映画『教皇選挙』は、物語としても、密室で行われる『教皇選挙』の具体的な様子を知ることができる史料的な面でも、すごく興味深い作品でした。映画で描かれていたことが、どこまで正確なのか、僕には、知るすべはないけれど。
実際の教皇選挙では、アメリカ出身のレオ14世が新しい教皇に選ばれました。
日本でも「誰が次の教皇になるのか?」というのは、けっこう話題になっていて、いろんな人の名前が挙がり、これまでの経歴、同性愛や妊娠中絶、移民政策などの課題へのスタンスが紹介されていました。
「保守派」と「改革派」どちらから次の教皇が出るのか?
日本の首相指名選挙のような「政局」的な報道が多かったのです。
正直、僕も実際に読み始めるまでは、この新書は、「ローマ教皇」という存在がうまれてからの「教皇史」や「事前の予想ではほとんど名前が挙がっていなかったロバート・プレポスト枢機卿が『レオ14世』になるまでの舞台裏での闘争が書かれているものだと思い込んでいました。
我が国のマスメディアで「教皇」が取り上げられるさいには、どうしても宗教色を脱色したような仕方で取り上げられがちである。教皇フランシスコが来日したさいに、多くのメディアが「核兵器」や「原発」や「死刑」といった問題に焦点を当てながら報道していたように。
たしかに、多くの人がキリスト教についての深い理解を持ってはおらず、キリスト教的な事柄についての関心をさほど持ってはいないかもしれない現代日本において、多くの人が視聴するテレビ番組で「教皇」を取り上げようとする場合には、宗教色を脱色して、ある種の普遍的なメッセージの語り手として取り上げるのが無難なやり方なのかもしれない。
だが、当然ながら、そのようなやり方では、「宗教者」である教皇の全体像を捉えることはできない。また、一見教皇が一般的なメッセージを語っているように見える場合であっても、その背後には必ず、キリスト教的なヴィジョンがある。そのキリスト教的なヴィジョンをある程度理解しておいてはじめて、教皇が語っている「普遍的」なメッセージも真の意味で理解することができるのである。
日本でキリスト教の教会が話題になるのは、スキャンダルや各国の要人との関係などの「政局」関連がほとんどです。
「カトリック教会の代表者として、宗教家としての教皇の考え」がメディアで紹介されることはほとんどありません。
この新書で、著者は、ベネディクト16世、フランシスコ、レオ14世という最近の3人の教皇の発言や論文、信徒たちに向けたメッセージなどを引用し、「神の代理人」としてのそれぞれのスタンスや、人々が宗教を信じることが難しくなった時代に、教皇は何を信徒たちに伝えてきたのかを紹介しています。
僕には、ベネディクト16世は「高齢、体力的な限界で『生前退位』した教皇」、フランシスコは「庶民派で、親しみやすい印象の人」、レオ14世は「まだよくわからない」という程度の印象しかないのですけど。
「この現代社会、インターネット時代に『神』なんて言われてもねえ……」みたいな気持ちがあるのです。
でも、世の中の人々が、僕と同じように「神を信じられなくなっている」ことは、教会側もちゃんと理解していて、かつ、これまで積み上げられてきた「神についての研究や考察」を踏まえて、信徒をはじめとする世界中の人々にメッセージを発し続けています。
僕自身、若い頃は「宗教なんて、集団幻想みたいなものだろう」と思っていました。
ヨーロッパの「神学」も、「神の存在を証明するためのこじつけ」みたいなものだと考えていたのです。
しかしながら、この本で紹介されている教皇たちの言葉を読むと「神を必要としてきたのは人であり、神の存在を証明するために、大勢の人々が知性と理性を尽くして、議論を重ねてきた歴史の積み重ね」の奥深さに圧倒されてしまうのです。
教皇フランシスコは、新型コロナウイルスのパンデミック発生直後の2020年3月に特別な「ウルビ・エト・オルビ(「都市(ローマ)と世界へ)」の祝福とメッセージを送っています。
この「ウルビ・エト・オルビ」をはじめ、(2020年)4月後半までになされた講話や執筆された書簡など八つの文書を収めた書籍が2020年6月にバチカン出版局から出版され、日本語訳も7月に『パンデミック後の選択』というタイトルでカトリック中央協議会から刊行された。その中に含まれている「再起計画」という論考の中で教皇は次のように述べている。
私たちは、保身のために逃げ出した人のようにではなく、懸命に、犠牲を払って在宅指示を守り続け、そうしてパンデミックを食い止めようとする地域の人たちや家族の姿を目の当たりにしています。
いかに多くの人が、排斥と無関心のパンデミックに襲われてきたか、そしてなお苦しんでいるかに気づくことができました。もがきながら、助け合い、どうにか堪えてきたから、今の状況の苦しみを和らげることができる(できた)のです。(「再起計画」、教皇フランシスコ『パンデミック後の選択』所収、カトリック中央協議会、2020年、51~52ページ)
この箇所をなぜ引用したのかというと、この書物のキーワードである「無関心のパンデミック」という表現が登場する箇所だからである。教皇フランシスコは、教皇就任当初から、「無関心のグローバリゼーション」という言葉を使って現代世界に対する根本的な批判を展開してきた。現代世界においては、情報や文化、政治経済の動向などが国境を超えて地球規模で瞬時に影響を与え合う一方で、一人ひとりの個人や共同体が自己利益を最優先させ、弱い立場の人々や世界の周縁に置かれてしまっている人々の苦境に対して無関心になってしまう傾向が強まっている。「政治」や「経済」や「文化」のみではなく、「無関心」というのもまた世界規模で広がってしまっている。教皇フランシスコはそう警鐘を鳴らし続けてきた。
「グローバリゼーション」が進むなかで、人々の心はむしろ、「自分の利益を優先し、見たくないものは見ないようにする、あるいは、他者への気遣いを失ってしまいつつある」。
この本のなかでに、有名な『善きサマリア人』の話が出てくるのです。
移民排斥に対して、「まずは自分の身近な人、『隣人』を助けるのが当然、それはキリスト教の教義にも適っている」というアメリカのヴァンス副大統領の言葉に対し、教皇選任前のプレポスト枢機卿が「隣人とは誰か」について反論・批判しています。
『善きサマリア人』については、上記リンクを読んでいただきたいのですが、「隣人愛」とは、血縁とか民族とか属性に基づくものではない、というのが、プレポスト枢機卿の考えなのです(そしておそらく、現在のカトリック教会の見解でもあるはずです。
レオ14世はアウグスチノ会(13世紀にアウグスティヌスの会則に則って生活していた修道士たちによって設立)に属していて、聖アウグスティヌスの影響を強く受けています。
また、アウグスティヌスは、次のような言葉も残している。
この世の順境はわざわいなるかな。しかも、一つならず二重の意味で。すなわち、順境のうちにはいつか逆境が来はしないかという恐れがあり、また、順境のよろこびがいつかは滅びるという二重の意味で。この世の逆境はわざわいなるかな。それも、一つならず二つならず三重の意味で。すなわち、逆境においてはたまらなく順境が恋しく、また、逆境そのものがつらく、また、いつか逆境にたえきれなくなる危険があるという三重の意味で。
まことに、地上における人間の生は、間断のない試練ではないでしょうか。
(『告白』第10巻第28章、山田晶訳、中公文庫、第2巻、299ページ)
このテクストにおいては、アウグスティヌスの不安な心が凝縮して表現されている。注意しなければならないのは、これは、アウグスティヌスがキリスト教に対する信仰を持つようになる前の心の状態について語っているのではなく、キリスト教の信仰を持つようになった後の心境が語られているものだということである。
幸福にみえるときも、思うようにいかないときも、生きていると不安や恐れから逃れることはできない。
信仰を持っていても、人間は、そういうものなのだ。
僕はこれを読んで、「そうだよなあ」と共感するとともに、「聖人」と呼ばれる人でさえ、そんな感情から逃れることはできなかったのか、と落胆と安心が入り混じったような気持ちになりました。
結局のところ、科学技術で周囲の環境が変化しても、人間そのものは2000年くらいでそんなに変わるわけではないし、「悩みどころ」もある程度普遍性があるような気がします。
信仰の対象とするかどうかはさておき、「ローマ教皇」というのは、こんなすごい人なんだな、「神学」というのは、「神を信じずにはいられない人間が、長年積み重ねてきた『生きる苦しみを和らげるため、より良く生きるための知見』」なのだな、と思いました。
結局、それぞれの人が、自分に都合が良いように、「神」やその言葉を解釈してしまうのも、「人間らしさ」なのでしょうけど。