
- 作者: 東海林さだお
- 出版社/メーカー: 朝日新聞出版
- 発売日: 2016/11/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
内容紹介
食べ物への好奇心と探求心は健在!
「秋刀魚の歌」のさんまは
ブロッコリーはなぜ暗いか
鴨に目覚める
梨に疑惑あり
いつか「大豆感謝の日」を
海鮮丼の悲劇
焦熱地獄グラタン
牛肉弁当、
シウマイ弁当と化す
・・・などなど。
人気シリーズの最新刊、第39弾!
東海林さだおさんが『週刊朝日』に連載されている「あれも食いたい これも食いたい」シリーズの第39弾。
巻末の東海林さんのプロフィールを眺めていたら、「1937年東京生まれ」とあったので、もうすぐ80歳になられるんですね。
このシリーズに関しては、良くも悪くも「安定感」に溢れているのですが、もうこれは偉大なるマンネリというか、「食べる」という行為に、これだけの情熱と観察力を傾け続けているのは、本当にすごいことだな、と。
東海林さんの感性とか好奇心っていうのは、尽きることがないのだろうか。
NHKのBS1に、
「COOL JAPAN」
という番組がある。
外国人から見た日本の文化、風習などをテーマに取り上げ、カッコイイ、とか、びっくりしたとかの感想を述べ合う番組である。
この間取り上げたテーマは、
「日本人は果物の皮をむいて食べるがそのことをどう思うか」
であった。
日本人がリンゴや梨や柿の皮をナイフでむいているシーンが映される。
そのシーンを見た外国人たちが、いっせいに、
「シンジラレナーイ!」
と言ったのである。
リンゴや梨の皮をむいて食べるなんて、という驚きである。
そのシーンを見て、ぼくは、
「そんなことで驚くなんて、シンジラレナーイ」
と思った。
そうか、そうなのか……
僕も「果物は基本的に皮をむいて食べるもの」だと思い込んでいたのですが、それは「世界標準」ではないようです。
彼らはカットしてから皮をむく。
のだそうです。
そのほうが作業の回数は増えるし、最初にむいていくような螺旋状の長い皮はできないけれど、器用じゃなくてもできるのは確かです。
どちらが合理的かというと、「カットしてからむく」ほうかもしれませんよね。
また「さんまを食べると、なぜ『しみじみする』のか? 鰯や鯵だとしみじみしないのに」という疑問に対しては、こんな考察をされています。
そのわけは、さんまの長身にあった。
さんまは鰯や鯵に比べて胴が長い。
さんまの平均身長は25センチ。
鰯や鯵は平均20センチ。
つまり5センチ、鰯や鯵より背が高い。
5センチ背が高い、じゃなかった、長身ということは、魚の場合は胴体の部分が長いということになる。
5センチ胴が長いとどうなるか。
5センチ分、鰯や鯵より食べるのに時間がかかる。
5センチ分、この魚とつきあっている時間が長くなる。
5センチ分長くつきあっているとどうなるか。
そこに人情が生まれる。
人間もそうだが、その人と長くつきあっていると人情が生まれてくるのは誰もが経験することである。
人情とは何か、愛である。
いつくしみである。情けである。
つまり、人間とさんまが情愛の関係で結ばれたことになる。
ああ、人とサンマの、秒速5センチメートル!
いい大人が、こんなことを大真面目に考察し、日々新しい発見をしているのです。
東海林さだおさんって、本当にすごい人だと思う。
そして、この理論も、なんだそれは、と思いつつも、「完全に的外れ」とも言いがたいところがすごい。
あと、こんな「ちょっとした発見」も。
今回、フタについて書くために辞書を引いていたら「後家蓋」というのが出てきた。
何だと思います? 後家蓋。
急須などの本体が毀(こわ)れてしまって残されたフタ。
逆に、フタのほうが毀れて、他の急須のフタで代用するフタのことをいうそうです。
「後妻業」なんていうのもあるそうですが、「後家蓋」というのは初めて知りました。
そもそも「後家」という言葉も、いまはあまり使われていないですよね、少なくともあまりポジティブなイメージではありませんし。
読んでいて、「すごく面白い」というよりは、「これ、シリーズのどこかで似たような話を読んだことがあるんじゃないか」とか考えながらも、ついつい読み進めてしまう、そして、やっぱり上手いなあ、って感心してしまう、そんな「職人芸」を堪能できるエッセイ集です。
「軽く読める」とずっと思っていたけれど、あらためて読んでみると、頭のなかだけで完結したり、思い出を語るだけではなく、自分で料理をしてみたり、物産展に出かけてみたり、すごく手間暇かけて書かれているのだよなあ。
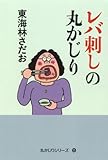
- 作者: 東海林 さだお
- 出版社/メーカー: 朝日新聞出版
- 発売日: 2013/02/04
- メディア: Kindle版
- この商品を含むブログを見る




