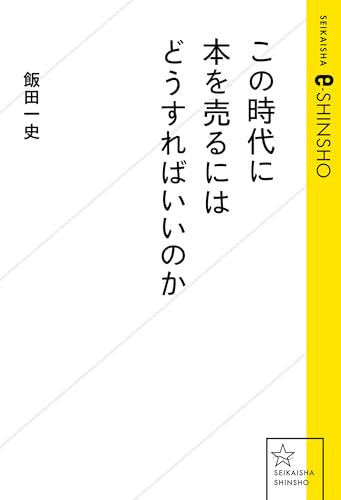Kindle版もあります。
日本人の本の「読む量」は減っていない。「買う量」が減っている。
『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』の著者による、本の「売上を伸ばす」ための提言。「本が売れない」と1990年代後半から言われ始め、四半世紀以上経った。書店の閉店が相次ぐなか、2024年以降、国策による書店振興への取り組みが話題を集めた。だが、それらで語られている現状分析には誤りが含まれている。出版産業の問題は読書(読む)量ではなく購買(買う)量である。本書ではまず、出版業界をめぐる神話、クリシェ(決まり文句)を排して正しい現状を認識する。その上でデジタルコミック、ウェブ小説、欧米の新聞や出版社、書店の先進事例やマーケティングの学術研究から判明した示唆をもとに、出版社と書店に共通する課題ーー「売上を伸ばす」ために何ができるかを提案していく。
著者の飯田一史さんが書かれた『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』を、以前読みました。
「本が売れない」「町の書店がどんどん潰れている(というか、もはや潰れ尽くしている感もあります)」という世の中の見かたに対して「もともと書店というか、『本』は儲かる商品ではなく、『書店』は本以外のものを売ることによって生き延びてきた」という歴史的事実を検証した興味深い内容でした。
実際、「町の本屋さん」や「郊外型書店」は、ものすごく減ってしまったけれど、最近はネットでの動画配信サービスの影響で、レンタルDVD(ビデオ)+書店、だったTSUTAYAのレンタルDVDのコーナーがどんどん縮小していき、かえって「本屋」に回帰している印象もあります。
この本は、「本が読まれなくなった」わけではなくて、「本が売れなくなった」のが(本に関する商売に従事している人たちにとって)問題なのだ、という前提に立って、「本を売るにはどうすればいいのか?}が検討されています。
まず最初に、ベストセラーになった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著)の内容について、本当に「働くこと」と「読書量」に関連があるのか、この本の内容は公表されているデータに対して、統計的に正しい判断がなされているのか、をかなりページを割いて書かれているのです。
まず『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』というタイトルからして、事実に即していない。日本の読書統計では、小中高と学齢が進むにつれて書籍の読書率・読書量が減る。だが高校以上になるとほとんど増えも減りもしない。つまり働き始める前にすでに読書量は減っている。働き始めたからといってそれ以上、減るわけではない(増えるわけでもない)。
書籍の読書量は、全国学校図書館協議会「学校読書調査」によれば、2025年時点で小学生は平均月12.1冊、中学生は3.9冊、高校生は1.4冊。日本人全体で冊数の平均を算出している調査は近年存在しない。2019年まで実施されていた毎日新聞社「読書世論調査」では2019年時点で1.5冊。文化庁が「国語に関する世論調査」で5年に一度実施している読書調査で1か月に読む本の冊数の割合を見ても「読まない」「1、2冊」「3、4冊」「5、6冊」「7冊以上」いずれも年齢による差はとぼしい。
もっとも、16~19歳は月1、2冊が22.9%、40~49歳や60~69歳が約30%であるのより低い。また月3、4冊が8.4%であり全世代で最多である。10代後半は相対的には本を多く読む。しかし劇的に違うとまでは言えない。月2冊以下の人たちが全体の約9割を占める。月3冊以上読む人たちはもともと全体の1割程度しかいない。月7冊以上読む人は3%未満だ。この点は全世代で共通している。これで「働いていると本を読めなく(読まなく)なる」とは言えない。働く前から平均的にはたいして読んでおらず、働いてからもたいして変わっていない。
ちなみにこれは日本以外の国では必ずしもそうではない。
ブラジルや韓国など、年を取るほど顕著に本を読まなくなっていく国もある。しかしいずれの場合も労働を機に劇的に変化があるわけではない。
『なぜはた』は労働時間と読書に強い関係があるという前提に立って書かれている。だが定量的にはその前提自体が誤りだ。
正直なところ、この本の前半部は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んでいないと、この本の著者の飯田さんが延々と三宅香帆さんに絡んでいるようにも感じます。
そもそも、『なぜはた』は、かなり売れた本ではありますが、社会現象になって常識化した大ベストセラー、というほどでもないと思うのです。
「読書時間と労働には相関はない。本は読まれていないのではなくて、買われていないだけだ、あるいは出版関係者が雑誌が売れていた昔ほど潤っていないだけだ」
『なぜはた』で示された「学生から社会人になって、本を読まなくなり、読むのも小説やファンタジー、SFから仕事に役立つ『自己啓発書』になっていく」という流れは、人が現実や社会に染まって「飼いならされていく」過程をみているようで、なんだかすごく説得力があるような気がするのです。
でも、実際のところは、「高校生くらいから一部の人を除いては本を読まなくなるし、就職したからといって読書量に大きな変化はない」みたいです。
この本で紹介されているデータをみていると、義務教育で「朝の読書の時間」を設けたのは、子どもたちの読書量を増やす効果があったのだな、と感じます。
それと同時に、「そうやってきっかけをつくっても、全体としては『本を読む人はずっと読むし、読まない人はやっぱり義務じゃなくなると読まない』のだな」ということもわかります。
僕自身は、けっこう様々なジャンルの本を読んできたし、今も読んでいるのですが、働き始めの、疲れ果てて仕事が終わったらもう寝るだけ、みたいな時期を除けば、読書量に一番影響しているのは、現在悩まされている「老眼」かな、という気がします。
本をたくさん読む人は、シンプルに「本を読むのが好き」で「読書が趣味、読書に向いている」だけなのではいかと。
ちなみに、「読書習慣の有無とスマートフォンの利用時間にはほぼ相関がない」というデータも紹介されています。
僕自身もスマートフォンをかなり利用しているのですが、その大部分は、なんらかの「文章」を読んでいる時間ですし、SNSの影響力を考えると、現在は「(とくに紙の)本は売れないが、文章を読み書きする能力は、かえって重みを増している」ようにも感じています。
「本が売れない」なかで、「電子コミック」は、さまざまなビジネスモデルで売り上げを伸ばし、マンガアプリやWEBマンガが「紙のマンガ雑誌」の売り上げや機能を代替していることも紹介されています。
「本が売れない」とされる時代でも、電子コミックは紙の単行本や雑誌とうまく置き換わり、書籍のなかでも堅調な売り上げを保っているのです。
また、WEB小説投稿サイト発の作品が、映像化をきっかけに、爆発的に認知度を上げ、その作品を生み出した投稿サイトがさらに注目されて作品が集まってくることも紹介されています。
この本のなかでは、ニューヨークタイムズの事例にもひとつの章が割かれています。
僕は、紙の新聞は売れなくなるし、ニュースはみんなインターネットで見るようになって、新聞やテレビなどの既存のマスメディアは斜陽化していく一方、だと思い込んでいました。
ところが、ニューヨークタイムズは、「直近では2000年段階と遜色ない営業利益率と純利益となっている」のです。
2000年から2015年くらいまでのニューヨークタイムズは収益も営業利益率も落ち続けていて、もうダメだと思われていたけれど、2011年に「デジタル課金」というシステムを導入し、2010年代中盤からデジタル中心に復活を遂げました。
ネットニュースは無料が当たり前、というのは、アメリカでは、すでに過去のものとなり、ニューヨークタイムズは、さまざまな工夫と経営戦略で、ユーザーに「課金」させるシステムをつくりあげました。
すごいといえばすごいけれど、日本で同じ方法で新聞社が立ち直れるとは言い切れないのですが。
また、欧米の大手出版社での動画やインフルエンサー、ポッドキャストなどで「知ってもらう」ための試みや「読書サイトなどを通じての口コミや交流でファンを増やす」仕組みについても紹介されています。
僕はずっと疑問だったのです。
直木賞や本屋大賞を獲ったような有名な作品は、すでに「売れている」あるいは「売れることがほぼ約束されている」のだから、それらの本の宣伝に時間やお金を使うくらいなら、まだ知られていない「隠れた名作」を大々的にプロモーションしたほうが、伸びしろが大きいのではないか、と。
著者は芹澤連さんやバイロン・シャープさんらのマーケティングの実証研究を紹介し、僕のこの疑問に答えてくれています。
メーカー(出版社)や小売店(書店)は、しばしばカテゴリーやブランドのヘビーユーザーに対してさらに買ってもらおうと施策を打つ。しかしヘビーユーザーは絶対数が少ない。そしてすでに限界近くまでたくさん買っている。だからこそヘビーユーザーなのだ。この人たちにさらに購入してもらうのは難しい。仮に多少購買頻度が増えても、ヘビーユーザーは少ない。そのため、全体で見たときの平均購入回数はそこまで大きく変化しない。
たとえば日本人が100人いたとして、現在の読書量は月2冊以下が9割だが、仮にこの人たちが今より1冊多く買えば全体で90冊増える。一方で月7冊以上読書する人は2~3%しかいない。この「本好き」の人たちに90冊分購買量を増やしてもらうには、ひとり30冊以上増やさなければムリだ。こうした算数から考えても「どうしたらまだ買っていない顧客やライトユーザーに+1回買ってもらえるか」が重要になる。
本書で何度も指摘してきたように、日本の出版産業では、雑誌の衰退とともに膨大な数のライトユーザーが本屋にほとんど行かなくなったことが問題だ。来店しなければ本屋で何か買うことはなく、売り場で目に入らなければその本を買わない。
もちろん既存顧客を無視していいわけではない。新規顧客と既存顧客の「両方」にアプローチしたときにもっとも大きな成果が得られる。これも研究からわかっている。
書店も出版社も、たくさん買っている「本好き」を大事にしてほしい、と思うのだけれど、「商売」として考えれば、「年に数冊、本を手にとったり、ネットニュースで『本屋大賞』の話題をみて興味を持ったりした人に、「プラス1冊」を買ってもらうことが大事なのです。そういう人のほうが、「圧倒的な多数派」なのだから。僕も「あと30冊」は買えないし。
この本で書かれているメインテーマ「今の時代に本を売るにはどうすればいいのか」については、著者自身も「決定的な解決策」は現時点では見出せておらず、今後も検証をつづけていく、と述べられています。
本好きとしては、出版社や身近な書店には生き残ってほしいし、これからも買い続けるとは思うのです。
僕が、というか人間がいくら本を読んで学んでも、ChatGPTにはかなわないよな、と、本の感想をAIと語り合いながら圧倒されてもいます。
その一方で、SNSやネットニュースで、事実とフェイクや宣伝との区別がつかない、あるいはそれらが入り混じった情報が拡散されまくっているのをみていると、「責任の所在がはっきりしていて、世に出る前にちゃんと吟味された本」の価値を思い知らされてもいるのです。